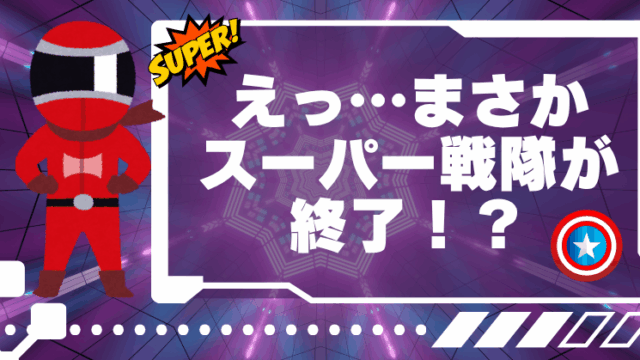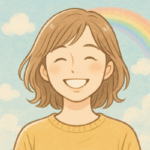ミヤネ屋放送終了理由の裏側は?視聴率低下と宮根60代の引退計画
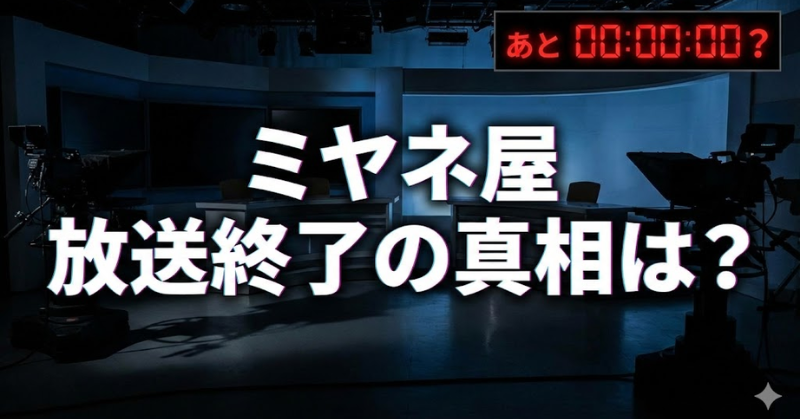
『情報ライブ ミヤネ屋』が、2026年9月末で20年の歴史に幕を下ろすことになりました。
長年、お昼の顔として親しまれてきただけに、驚かれた方も多いのではないでしょうか。
 画像引用:MANTANWEB
画像引用:MANTANWEB
MCの宮根誠司さんが還暦を機に、新たな挑戦を決意されたことが理由とのことですが、 視聴率競争の激化や、時代の変化も無関係ではないはずです。
この記事では、ミヤネ屋終了の背景にある時代の変化、宮根さんの本音、そして読売テレビの今後の戦略について、 詳しく解説していきます。
なぜ今、ミヤネ屋が終わるのか?
その真相に迫ります。
お茶の間の顔が直面する時代の変化
『情報ライブ ミヤネ屋』は、2006年7月にスタートしました。
当初は関西ローカルの番組だったのが、2008年3月からは全国ネットへと進出し、 2026年3月には放送回数5000回を達成した、まさに長寿番組ですよね。
しかし、近年は視聴率競争が激化しているんです。
TBS系の『ゴゴスマ』に、関東・名古屋・関西の3大都市圏で個人視聴率を抜かれる事態も発生しました。
特に、関西での敗北は、番組にとって大きな痛手だったと言えるでしょう。
ビデオリサーチのデータによると、2025年度の『ミヤネ屋』の平均世帯視聴率は、関東地区で約4.5%だったのに対し、『ゴゴスマ』は約5.2%とリードしていたんです。
数字で見ると、その差は歴然ですよね。
さらに、コンプライアンスの厳格化も、番組に影響を与えました。
ワイドショー的な報道スタイルや、宮根さんの断定的なコメントが、SNSで炎上するケースが増加したんです。
2024年には、特定の政治的発言が「偏向」と批判され、X上で数万件もの批判投稿が拡散される事態も起きました。
ネットニュースの普及も、見逃せない要因です。
リアルタイムでの情報番組の需要が変化し、視聴者層の高齢化も課題となっています。
テレビを取り巻く環境は、大きく変わってきているんですね。
- 視聴率競争の激化と敗北
- SNS炎上リスク増加
- 高齢化と需要の変化
宮根誠司が抱く「終活」への本音
宮根誠司さんは、2026年2月12日の生放送で、 「まだ元気なうちに新しい挑戦をしたい」と語り、62歳という年齢を一つの節目と捉えていることを明かしました。
過去のインタビューでは、「帯番組の負担は大きい。いつかは後進に譲りたい」と話していたこともあります。
26歳から37年間続けた司会業に、区切りをつけたいという気持ちがあったのでしょうね。
関係者によると、宮根さんは体力面での限界も自覚しつつ、 「局アナ1年目のようにがむしゃらに働きたい」という思いが強いそうです。
常に新しいことに挑戦したい、という気持ちを持ち続けているんですね。
現在のレギュラー番組は『Mr.サンデー』のみですが、 今後は情報番組を続けたい意向を示しつつも、フリーアナウンサーとしての「引き際の美学」を意識していると分析されています。
自身のキャリアを冷静に見つめ、今後の道筋を考えているのではないでしょうか。
 画像引用:スポニチ
画像引用:スポニチ
- 62歳を人生の節目と捉える
- 体力面での限界を自覚
- 引き際の美学を意識
読売テレビが進める午後の大改革
読売テレビは、『ミヤネ屋』終了の背景として、若年層ターゲットへのシフトを模索していると報じられています。
広告収入の観点から、2025年度の『ミヤネ屋』のコア視聴率(13~49歳)は依然として首位を維持しているものの、 全体の個人視聴率低下がスポンサー離れの一因となっているとの指摘があります。
局内では、デジタルネイティブな若年層向けコンテンツの強化が急務とされ、 後継番組にはSNSやストリーミングとの連動を視野に入れた企画が検討されているようです。
時代の変化に対応するため、新たな戦略を打ち出そうとしているんですね。
読売テレビ社長は会見で「宮根氏の意向を尊重した」と述べ、 終了は局側の意向ではないことを強調しましたが、 ビジネス視点では番組刷新による収益構造の見直しが不可避とされています。
一方で、視聴者感情としては「昼の習慣がなくなる」というロス感も強く、 20年の歴史を惜しむ声が根強いです。
長年親しんだ番組が終わるというのは、やはり寂しいものですよね。
実は、『ミヤネ屋』の終了背景には、単なる視聴率低下や宮根さんの意向だけでなく、 テレビ業界全体が直面する「オールドメディアの限界」が潜んでいるんです。
ワイドショー形式の番組は、SNS時代において視聴者との双方向性が求められる中、 従来の「上から目線」と捉えられがちな進行スタイルが敬遠される傾向にあるんですよ。
宮根さんが「関西での敗北」をプライドの問題として受け止めたとの報道もありますが、 彼が地元を大切にする関西人としてのアイデンティティを反映しているのかもしれませんね。
宮根さんにとって、『ミヤネ屋』は単なる仕事以上のものだったのではないでしょうか。